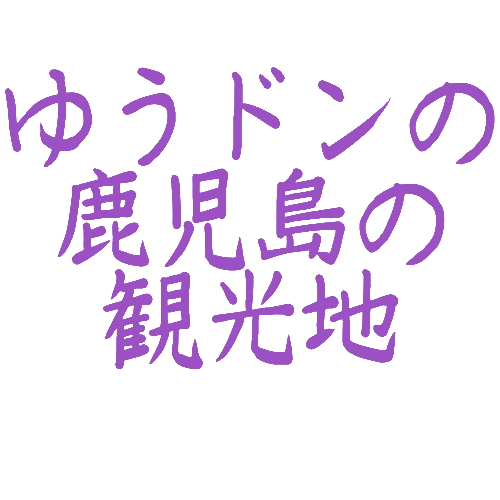鹿児島の歴史の息吹を感じる場所、石橋記念公園。ここには、かつて甲突川を渡る重要な交通の要所として、薩摩藩時代に築かれた石橋が今も静かに佇んでいます。その中でも、特に注目すべきは移設された五石橋。玉江橋、新上橋、西田橋、高麗橋、武之橋という名の五つの石橋は、その堂々たる構造で知られ、かつては車や歩行者が自由に行き交う生活の一部でした。しかし、水害により失われたその歴史を、石橋記念公園は静かに語り続けています。この公園を訪れることで、あなたは薩摩藩時代の息吹を今に感じることができるでしょう。
鹿児島の甲突川の石橋を移設して造った石橋記念公園
新しく造った石橋記念公園と以前からあった隣接する祇園之洲公園に、薩摩藩時代に造られた石橋を移設しました。
石橋記念公園には西田橋を移設して石橋記念館を造りました。祇園之洲公園には高麗橋、玉江橋を移設しました。
西田橋(石橋記念公園内)

西田橋は江戸時代、鶴丸城から江戸へ行く参勤交代で通る薩摩藩城下の玄関口でした。

1846年に木造の橋から石橋へ架け替えられました。

西田橋は、薩摩藩の威光と岩永三五郎の技術が発揮された傑作だと言われています。

鶴丸城跡の黎明館に復元した御楼門はこちら

高麗橋(祇園之洲公園内)

高麗橋は五石橋の中で、2番目に長い、4連アーチの石橋でした。

1847年に造られ、上流側には水切石が立てられ、また、川床には石が敷かれていて、ともに水の勢いを減らし橋を守っていました。

玉江橋(祇園之洲公園内)

玉江橋は、五石橋の中では、一番上流にあった橋で、最後に造られた四連アーチの石橋です。

当時、交通量が少なかったために、橋の幅が五石橋の中で一番せまい橋となりました。


石橋記念館は入館時間に制限がありますが、石橋公園、祇園之洲公園は気軽にいつでも行けますのでうれしいです。
両公園とも綺麗に整備されていて散歩に良い施設です。一度、来て見てください。
石橋記念館(石橋記念公園内)

平成5年(1993年)8月の8.6水害により、武之橋と新上橋は流失してしまいました。
そこで、残る『玉江橋』、『西田橋』、『高麗橋』の3つの橋を災害から守るのと、後世へ残す歴史的構造物として、この地へ移設し、石橋記念公園と石橋記念館を造りました。
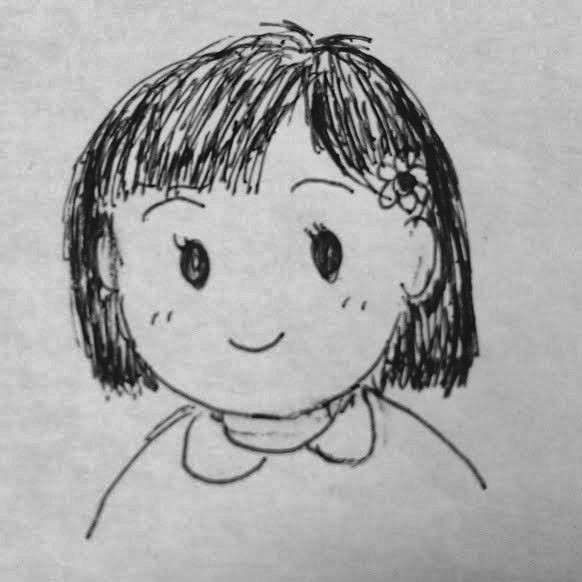 おんなのこ
おんなのこ西田橋は、石橋記念公園へ移設し、高麗橋、玉江橋は、祇園ノ洲公園へ移設しました。
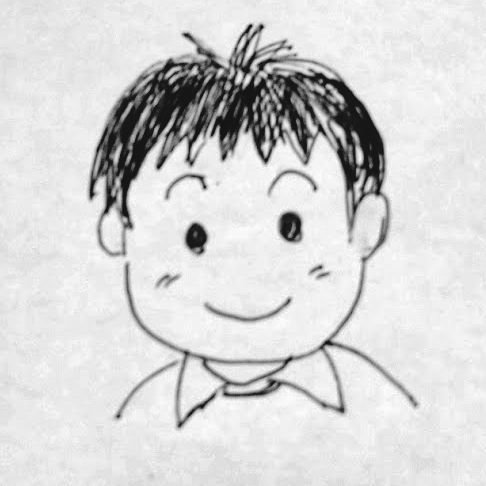
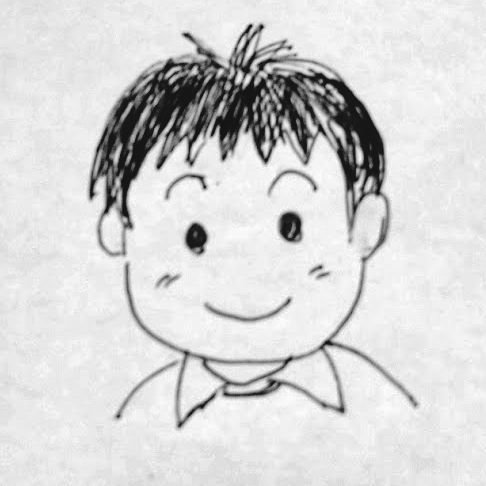
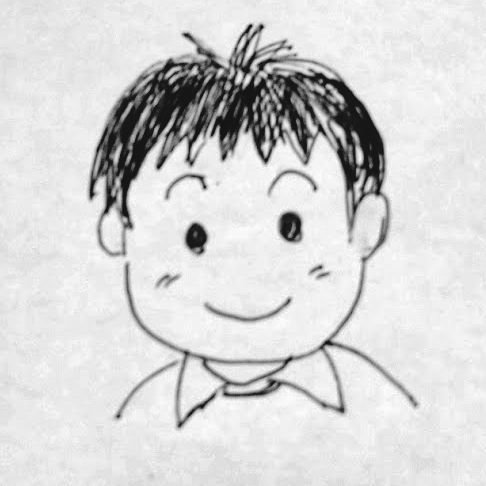
石橋記念館の常設展示室では、五石橋の歴史や架橋技術などについて展示しています。




特に、薩摩藩時代の土木事業についてのパネルや、石工の作業風景、ジオラマによる解説などは、その当時の状況が良くわかる展示になっています。


甲突川の五石橋に関する話
五石橋を架けた岩永三五郎


甲突川に架かっていた五石橋は、江戸時代末期に肥後(今の熊本県)の名石工である岩永三五郎によって架けられたものでした。
岩永三五郎は、1840年から1849年の間、薩摩藩にて五石橋の他、鹿児島市の永安橋、大乗院橋、稲荷橋、指宿市の湊橋、間橋、川内市の江ノ口橋等を架けました。
霧島神宮には岩永三五郎が作った、龍の形をした水の注ぎ口があります。
8.6(ハチロク)水害による五石橋の流失
平成5年(1993年)8月は、1日に鹿児島県姶良郡を中心に集中豪雨が、6日には鹿児島市を中心に集中豪雨が襲いました。
特に、8月6日に鹿児島市を襲った集中豪雨での大きな災害を『8.6(ハチロク)水害』と言います。
この日、甲突川が氾濫し、鹿児島市の都市機能は麻痺状態になりました。
バスや市電も止まり、天文館も浸水の被害を受けました。そして、甲突川五石橋の武之橋と新上橋が流失してしまいました。
【8.6(ハチロク)水害】 国土交通省 九州地方整備局 のホームページへ
石橋記念館の施設案内
| 住所 | 鹿児島県鹿児島市浜町1-3 |
| アクセス | JR鹿児島中央駅から車で約15分 |
| 市電:鹿児島駅前から徒歩約15分 | |
| JR鹿児島中央駅からカゴシマシティビューで約56分 | |
| 開館時間 | 9時~17時(7月、8月は19時) |
| 休館日 | 月曜日、年末年始 |
| 観覧料 | 無料 |
| 駐車場 | 無料 |
桜島港から歩いて行ける5つの観光地を紹介しています。また、
桜島港から車で行ける7つ(12)の観光地を紹介しています。


桜島観光をするには鹿児島市内のホテルをベースにするのが一番です。
桜島観光の参考に下の記事をどうぞのぞいてみてください。